
Vol.154「世界陸上と国スポ」
9月13日(土)から21日(日)に国立競技場で「東京2025世界陸上競技選手権大会」が開催されました。世界選手権の日本での開催は、2007年大阪大会以来で18年ぶりとなります。東京での開催は、1991年以来で、日本での開催は3回目となります。1991年の世界選手権、実は私、出場しています。

1991年は選手として、2007年は短距離のナショナルコーチとして、参加させていただきましたが、今回は400mHの井之上駿太選手(富士通)の専任コーチとして参加してきました。
陸上競技に関わるものとして、大会が成功すること、観客が集まってくれるのかということを心配していましたが、男子棒高跳びでアルマンド・デュプランティス選手(スウェーデン)が6m30の世界新記録をマークし、男子400mや混合マイルリレー、女子3000m障害などで日本新記録も樹立されるなど、大会は大変な盛り上がりでした。
メディアでも大きく取り上げていただきました。観客数も日本の陸上競技大会の最大数を更新する61万9288人で、世界選手権は、大成功であったと言えます。TBSテレビによる、事前の宣伝や、織田裕二さんの復活や番宣も多大なる影響があったと思います。
スタジアムの観客席で観戦しましたが、日本人選手への声援は、耳が痛くなるほど盛大で、海外選手にも同じように大きな声援が送られていました。このような中でパフォーマンスすることは、選手の気持ちを高揚させ、言葉で表現するのが難しい感覚になります。この感覚を再び味わいたくて競技を継続する選手も多いと思います。

この大会は、観せ方も工夫がされていました。気が付いた方もいらっしゃると思いますが、フィールド競技の決勝が、通常のルールと異なった展開にしてあり、より盛り上がるようになっていました。
通常、フィールド競技の予選は、出場者全員が3回の予選試技を行います。そして、その予選試技のうち、設定された予選通過標準記録を突破するか(1回目で突破すれば1回で予選通過)、予選通過者を含め、記録の上位12名が決勝に進出できます。もし、予選通過標準記録を13名以上が突破した場合は、突破した全員が決勝に進出できます。
残念ながら予選敗退となってしまったやり投げの北口榛花選手(JAL)は、予選の記録が60m38でした。予選通過標準記録は62m50でしたので突破の記録に届きませんでした。予選通過標準記録の62m50を予選で出して決勝進出を決めた選手は6名いました。
あと6名が決勝に行けるのですが、12番目の記録は60m98で、北口選手は惜しくも届かず(14番目)、予選敗退となってしまいました。北口選手の自己ベスト記録は67m38ですから、ケガの影響が大きかったのでしょう。早く治して元気で明るい姿を見せてほしいですね。
通常のルールでは、決勝に進出すると、まず、全員3回の試技ができます。3回を終えると、その3回の記録上位8名がさらに3回試技を行うことができます。そして、合計6回の試技で勝負を決します。後半の3回の試技順は、前半3回の記録の下位から順に試技を行います。つまり、記録の良い人が最後に試技を行うような設定になります。
今までの世界選手権でも、観客により楽しんでもらうため、後半の2回までの試技の結果から、最後の1回だけを順番をさらに変更し、記録の良い人が最後に試技をできるように変更していました。そして、今回はさらに変更を加え、より盛り上がるように手を加えました。
それは、10・8・6ルールというもので、決勝の前半3回終了時、10名が4回目の試技を行うことができます(通常は8名)。そして、その10名は、4回目の記録によって上位8名に絞られます。つまり5回目は8名が試技をします。次、6回目の試技に進めるのは6名です。競技できる人数を変更することで、より戦略が必要になり、競技者にとっても、観る人にとってもスリリングな展開になりました。
陸上競技は、地味な印象があって、人気があるとは言い切れません。音響やライトアップを効果的に使用したり、選手の入場や紹介も工夫されたりして、魅せる陸上競技ということで、いろいろ考えているのですが、まだまだ人気競技と比べると劣っているように感じます。
10月3日からは、滋賀県で開催された国民スポーツ大会に行ってきました。神奈川県は天皇杯(男女総合)7位、皇后杯(女子総合)3位の成績でした。昨年の大会では、天皇杯10位、皇后杯9位でしたので、活躍してくれましたね。皇后杯は優勝した兵庫県とわずかに5点差でした。

横浜市関係では、少年男子Aやり投げで、森村学園高校の松本一颯選手が63m49を投げて見事に優勝してくれました。松本選手はまだ高校2年生です。さらに、少年男子共通110mハードルで優勝した、古賀ジェレミー選手(東京高校)は、東京都の代表選手なのですが、出身中学は保土ケ谷中学校です。
古賀選手の記録は、13秒07でU20日本記録です。U20のハードルはシニアよりも低い99.1センチなのですが、この記録はU20の2025年の世界ランキング4位に相当します。近年、男女ともに日本のショートハードルの活躍が顕著であり、シニアでも村竹ラシッド選手(JAL)が、8月に福井の大会で樹立した12秒92という日本記録は、現在2025年の世界ランキング2位に君臨しています。
村竹選手は、東京の世界選手権は惜しくも5位に終わってしまいましたが、メダル獲得まであとわずかで、手が届くところに到達しています。3位まではわずか0秒06差でした。武相高校出身の泉谷駿介選手(住友電工)もいますし、日本のレベルはアメリカ、ジャマイカに次ぐレベルにあると思います。
来年は、世界レベルの大会はありませんが、アジア大会が名古屋で開催されます。さらに翌年2027年は北京で世界選手権が開催されます。アジア大会での金メダル獲得はもちろん、世界選手権では複数名の決勝進出、メダル獲得も現実味を帯びてきました。楽しみでなりません。
9月の世界選手権は本当に良い大会となりました。そして、世界選手権に出場した日本代表選手が多数出場した国スポも大いに盛り上がりました。世界選手権は、陸上競技の大会がもっと人気が出るということを認識させてくれる大会であったと思います。
競技のみならず、観せる、魅せるということをもっと考えることで陸上競技の大会を魅力のあるものにできます。皆さんからのご意見もぜひ伺いたいですね。
1969年5月8日生まれ、横浜市南区出身。
元オリンピック陸上競技選手。横浜市立南高等学校から法政大学経済学部、富士通、筑波大学大学院で競技生活を送る。
現在は法政大学スポーツ健康学部教授 コーチ学(スポーツ心理学) 同大学陸上競技部監督 法政アスリート倶楽部代表 日本陸上競技連盟強化委員会ディレクター兼オリンピック強化コーチ(ハードル)。
2007年から日本陸上競技連盟強化委員会の男子短距離部長を務め、世界選手権(2007大阪、2009ベルリン、2011大邱、2015北京、2019ドーハ)、オリンピック(2008北京、2012ロンドン)に帯同。
また、2014年には日本陸上競技連盟の男子短距離部長へ復帰し2016リオデジャネイロオリンピックに帯同し、日本短距離男子チームの責任者として同行した。
1990年代を代表する陸上競技者として活躍。1996年のアトランタと2000年のシドニーオリンピックに出場、世界室内陸上競技選手権大会400mで銅メダルを獲得するなどの活躍を見せた。元400mハードル日本記録保持者。
ブログ
※タイトル・本文に記載の人名・団体名は、掲載当時のものであり、閲覧時と異なる場合があります。
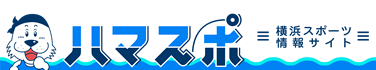 ハマスポ
ハマスポ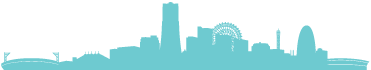
 お知らせ&トピックス
お知らせ&トピックス ページトップへ戻る
ページトップへ戻る ページトップへ戻る
ページトップへ戻る

